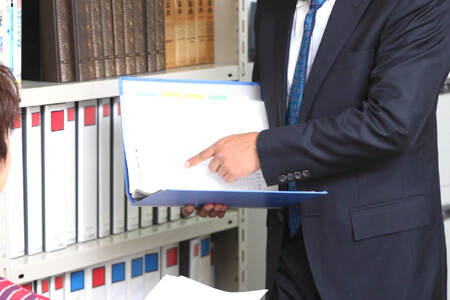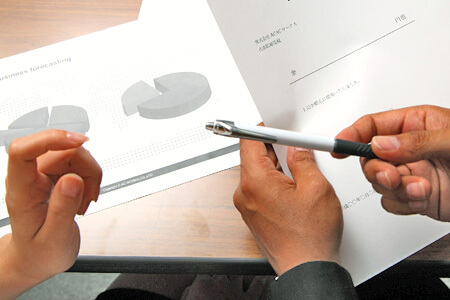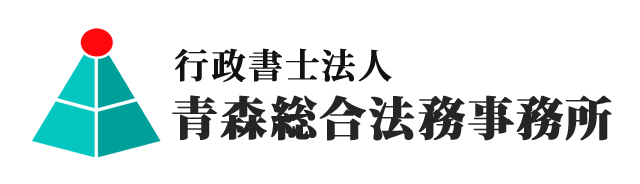建設業許可の記事
建設業許可を取得すると、許可業者としてしなければならない義務が発生します。
その一つが、主任技術者・監理技術者の配置です。
主任技術者
建設業者は、元請下請、金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。
この全ての現場に配置しなければならない技術者が「主任技術者」です。
監理技術者
発注者から直接工事を請け負った元請業者は、その下請契約の請負代金の額が3000万円以上 (建築一式工事の場合は4500万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、より上位の資格者等である「監理技術者」を配置しなければなりません。
専任義務
工事現場における「主任技術者」「監理技術者」が果たすべき役割は重大であり、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては、「専任」義務を負うこととなります。
※「専任技術者」は、「主任技術者」「監理技術者」になることはできません。
専任技術者とは、「建設業許可を取得するための要件」であり、一定の国家資格や実務経験を持つ者がなることができます。許可を受けようとする業種ごとに定める必要があり、「営業所ごと」に、常勤である必要があります。
一方、主任・監理技術者は、「工事現場」において、技術上の管理をつかさどる者として配置しなければなりません。
主任・監理技術者は、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、その請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事においては各工事現場ごとに「専任」でなければなりません。つまり、1人の技術者が同時に他の工事現場において、主任・監理技術者として工事を担当することはできません。
また、専任技術者も「専任」として営業所に常勤していなければならないため、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、その請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事については、主任技術者・監理技術者のどちらも兼ねることはできません。
費用
| 新規 | 更新・追加 | |
| 国土交通大臣の許可 | 150,000円 | 50,000円 |
| 都道府県知事の許可 | 90,000円 | 50,000円 |
法人成
建設業許可を受けて営業している個人事業主が、法人へと組織変更した場合には、個人事業として取得している建設業許可を法人に引き継ぐことはできません。
そのため、個人事業主の建設業許可については、廃業届を提出し、新たに法人として新規の建設業許可を取得する必要があります。
また、社会保険への加入義務も生じます。
これまで5名以内の個人事業主として適応除外であっても、法人として改めて建設業の許可を受けようとする場合、たとえ取締役が1人の株式会社であっても健康保険及び厚生年金に加入しなければなりません。
また役員以外の従業員を雇う場合には、雇用保険への加入義務も生じます。
許可換え、般・特新規
建設業の許可には、大臣許可と知事許可があり、どちらか一方の許可しか受けることが出来ません。
そのため、知事許可を受けている建設業者が、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けた場合には国土交通大臣へ新規申請をする必要があります。また、ある都道府県の知事許可を受けている建設業者が、その区域内の全ての営業所を全て廃止して、他の都道府県に本店を移転した場合や、大臣許可を受けていた建設業者が、1つの都道府県のみに営業所を残し、他の都道府県の営業所は全て廃止した場合には移転先の都道府県知事へ新規申請が必要となります。(許可換え)
また、建設業の許可には、一般許可と特定許可があり、これもどちらか一方しか受けることが出来ません。
そのため、現在一般建設業の許可のみを受けている建設業者が、許可を受けている業種またはそれ以外の業種について、下請契約の締結の制限を受けずに(元請として3,000万円以上の工事を下請に出す場合)営業をしようとする場合、特定建設業の許可が必要となります。また、現在特定建設業の許可を受けている建設業者が、技術者の退職・財産的要件を満たさなくなった場合など、特定建設業許可の要件を満たさなくなった場合は、一般建設業の許可を受け直す必要があります。(般・特新規)
用語の定義
- 工事経歴書
- 工事経歴書とは、直前1年間の建設工事を業種ごとに作成したものです。
- 会社を立ち上げたばかりで建設工事はしていないという場合でも、工事経歴書は必要です。「なし」と記入して提出します。
カテゴリー: 建設業許可 投稿日:2015年9月27日
- « 経営事項審査制度とは
- 許可後の手続き »
決算届出
建設業の許可を取得すると、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に、決算の報告をする必要があります。これが決算届出です。決算報告書は、通常の財務諸表と異なり、建設簿記に沿って作成する必要があるため、税理士が税務署に提出するために作成した決算書をそのまま使用することはできません。
建設業用の決算書に変更して作り直す必要があります。
毎年の届出をしていない場合には、建設業許可の更新手続きをすることができなくなってしまいますので注意が必要になります。
変更届出
- 変更届は、下記の事項に変更が生じた場合に、提出が必要となります。
- ・商号や名称の変更
- ・既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
- ・資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更
- ・個人の事業主または支配人の氏名の変更
- ・経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更)
- ・専任技術者の変更(氏名の変更)
- ・営業所の新設
- ・新たな営業所の代表者の発生
- ・経営業務管理責任者または選任技術者の要件が欠けた
- ・使用人数の変更
- ・令3条に規定する使用人の一覧表の変更
- ・国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
更新
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があります。申請が遅れると更新することができなくなり、新たに建設業許可を取り直さなければなりません。その間、500万をこえる工事を請負う事はできません。
複数の許可がある場合には、それぞれの業種毎に有効期間が違う場合がありますが、更新にあわせて、それぞれの業種の有効期間をそろえることもできます。(一本化)
また、以下の場合には、更新を受けることが出来ませんので、注意が必要です。
毎事業年度終了後に提出する決算届出が出されていない。
役員の変更や、商号・所在地等の変更届出が出されていない。
業追
業種追加とは、ある業種の建設業許可を受けている者が他の業種の許可を取得する申請をいいます。例えば建築一式工事業の許可を取得している業者が、新たに大工工事や内装仕上げ工事業を追加取得するなどの場合をいいます。
業種追加は、既に許可を取得している状態のためおよその要件は整っていますが、経営業務の管理責任者について「許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上の経験」または「許可を受けようとする建設業の業種以外の業種に関して7年以上の経験」が必要になることに注意が必要です。
専任技術者についても、希望する許可業種の専任技術者となり得る有資格者が必要となります。
カテゴリー: 建設業許可 投稿日:2015年9月27日
| 1 | 建設業許可申請書 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 建設業許可申請書別表 | |||
| 3 | 工事経歴書(直前1年分) | |||
| 4 | 直前3年間の各事業年度における工事施工金額 | |||
| 5 | 使用人数 | |||
| 6 | 誓約書 | |||
| 7 | 経営業務の管理責任証明書 | |||
| 8 | 専任技術者証明書(新規・変更) | |||
| 9 | 専任技術者証明書(更新) | |||
| 10 | 使用者の一覧表 | 11 | 国家資格者・監理技術者一覧表 | |
| 12 | 許可申請者の略歴書 | 13 | 使用人の略歴書 | 14 | 定款 | 15 | 株主(出資者)調書 | 16 | 財務諸表 | 17 | 登記簿謄本(法人のみ) | 18 | 営業の沿革 | 19 | 所属建設業者団体 | 20 | 納税証明書 | 21 | 主要取引金融機関名 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
- 確認書類
- これらの許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の国家資格証の原本や、保険の加入状況を確認するための領収書など、確認書類が必要となります。
カテゴリー: 建設業許可 投稿日:2015年9月27日
建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていることと「欠格要件」に該当しないことが必要です。
経営業務管理責任者が常勤していること
経営業務管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者をいいます。
- 経営業務管理責任者になる者は、
- ・法人の場合、常勤の役員(株式会社や有限会社の取締役など)
- ・個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人
- ・許可を受けようとする建設業に関し5年以上
- ・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上
たとえば、土木工事と塗装工事を営んできた経験が5年以上ある法人の役員又は個人事業主は、土木工事と塗装工事の経営業務管理責任者となることができます。
また、特定の建設業種に関し、7年以上の経験がある場合、28業種全ての経営業務管理責任者となることができます。
- この経験年数は、
- ・証明者が建設業許可を有している場合には建設業許可の指令書
- ・証明者が建設業許可を有していない場合には期間分の請負契約書や請求書、注文書 などで証明します。
なお、経営業務管理責任者の経験は、現在の会社での役員経験に限られません。
前職で株式会社の常勤の取締役や個人事業主であったのなら、その裏付書類を示すことで経営業務管理責任者の経験として認められます。
専任技術者が常勤していること
専任技術者とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者で、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。
専任の技術者の要件は、一般の許可か、特定の許可で異なります。
- 一般許可の専任技術者になるには、
- ・大学(短大・高専含む)の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験がある
- ・学歴、資格の有無を問わず、申請業種に関して10年以上の実務経験がある
- 特定許可の専任技術者になるには、
- ・一般許可の専任技術者の要件のいずれかに該当し、且つ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験がある
- ・許可を受けようとする申請業種に関して国家資格をもっている
実務経験とは、28種類の建設工事のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する技術上の経験をいいます。したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの技術を修得するためにした見習中の技術的経験も含まれます。
実務経験を証明しようという場合は、実務経験証明書を会社の代表者等に証明してもらう必要があります。
- さらに、その裏付け資料として、
- ・証明者が建設業許可を有している場合には建設業許可の指令書
- ・証明者が建設業許可を有していない場合や、許可を有していても有している業種以外の業種を証明する場合には期間分の請負契約書や請求書、注文書
専任技術者は、許可を取ろうとする営業所の専任技術者であることと、常勤であることの両方が求められますので、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。
なお、専任技術者は要件さえ満たせば経営業務管理責任者と同一人が兼ねることができます。
常勤確認の方法
常勤とは、原則として経営業務管理責任者については本社・本店等において、専任技術者、令第3条の使用人については当該営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを意味します。
実際に営業所に通える距離に住んでいる必要があるため、住民票により、現在の住所を確認します。
- また、他の事業主に雇われていないかを確認するため、
- ・雇用保険被保険者資格喪失届の原本
- ・社会保険標準報酬月額決定通知書の原本
- ・社会保険被保険者資格取得確認通知書の原本
- ・健康被保険者証の写し
- ・住民税特別徴収税額通知書の原本
- ・確定申告書控の原本
- 法人は、第一表+役員報酬の内訳書
- 個人は、第一表+第二表
- ・給与台帳(源泉徴収簿)+出勤簿等3か月分
- ・その他、常勤が確認できるもの
誠実性
建設業者は請負契約に関して、不正または不誠実な行為をしてはいけません。
不正な行為とは、請負契約の締結または履行に関して詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為
不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて、請負契約に違反する行為をいいます。
財産的基礎
建設業においては、資材の購入や工事着工の準備など、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要になります。
その為、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準が求められます。
一般建設業と特定建設業とでそれぞれ要件が異なっており、特定許可では発注者や下請業者の保護という観点から一般許可よりも厳しい財産的要件が求められます。
- 一般建設業許可の場合
- 次の3つのうち、いずれかに該当する必要があります。
- ・自己資本の額(純資産合計)が500万円以上あること。
- 許可申請日直前の決算における貸借対照表の純資産合計の額で判断されます。
- 資金調達能力が500万円以上あると認められること。
- これを証明するために
- ・金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」
- ・金融機関が発行する「500万円以上の融資証明書」
- ・直前5年間許可を受けて継続して建設業の営業をしてきた実績のあること。
- 特定建設業許可の場合
- ・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- ・流動比率が75%以上であること。
- ・資本金の額が2,000万円以上であること。
- ・純資産の額が4,000万円以上であること。
欠格事由に該当しないこと
- 次のいずれかに該当した場合は許可を受けられません。
- ・許可申請書またはその添付書類の中の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
- 許可を受けようとするものが次のいずれかに該当するとき
- ・成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
- ・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- ・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- ・建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
- ・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- ・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
- ・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者
カテゴリー: 建設業許可 投稿日:2015年9月27日
大臣許可と知事許可
建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。
ひとつの都道府県にのみ営業所を設ける場合には知事許可を申請します。
同一都道府県であれば、2つ以上の営業所を設ける場合も知事許可に該当します。
これに対し、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可の申請となります。
例えば、青森県と秋田県に営業所を設ける場合等です。
なお、営業所とは、本店や支店など、常時契約の締結や見積もり、入札等、実体的な業務を行う者と技術者が常勤している場所を指します。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所などは営業所に該当しません。
一般許可と特定許可
建設業の許可には、一般許可と特定許可があります。
発注者から直接建設工事を請け負う元請業者が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)を下請に出す場合に特定許可が必要となります。
それ以外の場合は一般許可となります。
(特定許可が必要なのはあくまで元請として工事を請け負う業者のみであり、下請業者がさらに下請に出す場合、金額にかかわらず特定許可は必要ありません。)
カテゴリー: 建設業許可 投稿日:2015年9月27日